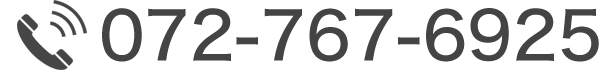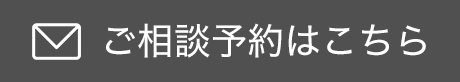高速道路での追突事故
第1 高速道路での追突事故における過失割合の考え方
高速道路は一般道路と異なり、高速走行が前提とされる特殊な交通環境です。そのため、交通事故の態様や過失の評価も一般道路とは異なる視点が求められます。
特に追突事故においては、加害者側の過失が重く評価される傾向にありますが、被害者側にも一定の過失が認定されるケースも存在します。本稿では、高速道路での追突事故における過失割合の基本的な考え方について、裁判例を踏まえて解説します。
第2 過失割合の基本的な考え方
1 過失割合とは、交通事故の発生に対する当事者双方の責任の度合いを数値で示したものです。交通事故における過失割合は、別冊判例タイムズ38号に基づき、事故類型ごとに基本の過失割合が定められています。高速道路における追突事故も例外ではなく、別冊判例タイムズ38号において類型別の基準が示されています。
2 そこで、代表的な事故類型ごとに基本の過失割合と修正要素について紹介します。
| 類型 | 被追突車の 基本過失割合 | 追突車の 基本過失割合 |
| ⑴理由のない急ブレーキによる追突【328】 | 50% | 50% |
| ⑵過失により駐停車中に追突された場合【320】 | 40% | 60% |
| ⑶過失なく駐停車中(退避懈怠あり)【323】 | 20% | 80% |
| ⑷過失なく駐停車中(退避懈怠なし)【326】 | 0% | 100% |
⑴ 【328】の類型は、被追突車が理由のない急ブレーキをかけた(道路交通法(以下「道交法」といいます。)24条)ために、追突車が追突した場合を想定しています(被追突車が事故を回避するために急ブレーキをかけた場合は除かれています。)。
一般道路及び高速道路のいずれにおいても「車両等の運転者は、危険を防止するためやむをえない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない」とされています(道交法24条)。しかし、高速道路[1]においては時速80㎞を超える高速度での走行が許容されており[2]、かつ、本線車道での駐停車が原則として許されていない(道交法75条の8第1項本文)ことに鑑みると、被追突車が急ブレーキをかけた場合の危険は一般道路のそれとは比になりません。したがって、①類型では、「追突車:被追突車=50%:50%」とされています[3](これに対して、一般道路における急ブレーキ事故は「追突車:被追突車=70%:30%」とされています。[4])。
なお、風景や事故見物のために急ブレーキをかけた場合には「著しい過失」が認められるとして、追突車側の過失が10%~20%減算されます。他方で、分岐点・出入口付近において追突事故が発生した場合には、追突車側の過失が10%加算されます。なぜならば、分岐点や出入口の付近においては、本線車道に進入しようとする他の自動車との関係で被追突車が急ブレーキをかけることが想定されうるため、追突車においてもあらかじめそのような事態を予測に入れて運転するべきだからです。
⑵ 【320】の類型は、事前の整備不良によるガス欠・エンジントラブルや自己に過失がある先行事故等により運転に支障を来して駐停車していた先行車両に、前方不注視の後続車が追突した場合を想定しています。
高速道路においては、「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない」(道交法75条の8第1項)とされています。したがって、本線車道等に自動車を駐停車させた場合には、一般道路におけるよりも事故発生の危険が高く、被追突車の過失が相当大きいといえます。そこで、②類型では、「追突車:被追突車=60%:40%」とされています。[5]
なお、被追突車が路肩等に退避できたのに退避措置を怠り、かつ、停止表示器材の設置が可能であったのにこれも怠った場合には「著しい過失」が認められるとして、追突車側の過失が10%~20%減算されます。他方で、被追突車が設置した停止表示器材等を認識することが可能であった場合には、追突車に「著しい過失」が認められるとして、追突車側の過失が10%~20%加算されます。[6]
⑶ 【323】の類型では、被追突車が自己に過失のない先行事故によって本線車道等に駐停車した後、退避可能であったのに退避しなかったか、又は、退避不能であったが、停止表示器材を設置することは可能であったのにこれを怠った場合を想定しています(②類型とは、駐停車したこと自体には過失がなかったという点で異なることに注意してください。)。そして、③類型の場合、被追突車が停車したこと自体については過失がないから、被追突車の過失の程度は②類型よりも小さいです。したがって、③類型では、「追突車:被追突車=80%:20%」とされています。[7]
なお、修正割合については、②類型と類似しているので省略します。
⑷ 【326】の類型では、被追突車が自己に過失のない先行事故によって本線車道等に駐停車した後、退避することが不可能であり、かつ、被追突車の運転者等が停止表示器材を設置したにもかかわらず追突事故が発生した場合を想定しています。このような場合には、被追突車は駐停車したことについての過失はなく、駐停車後の対応にも過失はないというべきですから、被追突車に対する過失相殺は否定されるべきです。したがって、④類型では、「追突車:被追突車=100%:0%」とされています。
なお、④類型においては、修正要素による修正がされないことに注意してください。
第3 判例紹介(大阪地判平成20年5月14日交事民集41巻3号593頁)
1 事案の概要
高速道路(片側二車線・下りカーブ・照明なし・最高速度80km/h)を走行する被告は、雨で濡れた路面を時速120〜130km/hで走行中、スリップしたことにより壁に衝突し、車両の前部が中央分離帯側を向いて斜めに停止しました(停車場所については下記の図もご覧ください)。その後、時速約100km/hで走行していた乙山が、被告車両に衝突したのが本件事故です。なお、被告は三角板や発煙筒などの警告措置を行っていませんでした。
(LEX/DBインターネットより引用)
2 裁判所の判断
まず、「高速道路上に、自己の落ち度により停車していた四輪車に、後方から走行してきた四輪車が追突した場合の過失の基本割合は、一般的には停車側よりも衝突側の過失の方が大きいものの、停車側の過失も決して少なくない」と判示しています。そのうえで、被告側の過失として、「制限速度を40㎞/h以上超過して走行し」「自車を制御できなくなったという重過失」(以下「過失1」とします。)と②「夜間視界不良な高速道路上に停止したこと」(以下「過失2」とします。)を指摘し、他方で乙山側の過失として、「制限速度を20㎞/h以上超過して走行したこと」(以下「過失3」とします。)と「被告車両の発見が遅れたという著しい過失」(以下「過失4」とします。)を指摘して、乙山と被告の過失割合を4:6としました。
なお、本件裁判例において、被告が発煙筒などの警告措置を行っていなかったことは修正要素となりえますが、裁判所は「停止と衝突が時間的に接着していたことに照らし、被告が停止後三角板や発煙筒を設置する等の安全措置をとらなかったことに過失があったとまでは言えない」として、修正要素とされていません。したがって、停止表示器材設置等がされていないからといって、直ちに修正要素として考慮されるわけではないことに注意してください。
3 裁判例の分析
本件事案は、被追突車が40㎞/hの速度超過により事故を引き起こしているため、自らの過失により停車中に追突されたといえます。したがって、本件事案は②類型に該当すると思われます。したがって、基本となる過失割合は「追突車(乙山):被追突車(被告)=6:4」となります。これを前提に、裁判所は過失1から過失4による修正を施すことで、「追突車(乙山):被追突車(被告)=4:6」という割合になったと思われます。
なお、修正要素による減算・加算は、別冊判例タイムズ38号により一義的に決定されるものではなく、事案に応じて適宜修正される場合もあります。
以上
交通事故の相談は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで
大阪オフィス
https://g.page/murakamishinosaka?gm
川西池田オフィス
https://g.page/murakamishin?gm
福知山オフィス
https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm
交通事故専門サイト https://kawanishiikeda-law-jiko.com/
[1] 高速自動車国道法4条1項に定める高速自動車国道及び道路法48条の2第1項に定める自動車専用道路を併せて「高速道路」という(別冊判例タイムズ38号P.461及び国土交通省HP参照)。
[2] 高速自動車国道は普通乗用車の場合、最高速度は100km/hとされています(道路交通法施行令第27条)。他方で、自動車専用道路の最高速度は一般道路と同様に60km/hとされていますが、標識や標示によって70km/hや80km/hに引き上げている区間もあります。(高速自動車国道と自動車専用道路の違いとは? | JAF クルマ何でも質問箱参照)
[3] 別冊判例タイムズ38号P.485,486参照
[4] 別冊判例タイムズ38号P.293,294参照
[5] 別冊判例タイムズ38号P.475,476参照
[6] 別冊判例タイムズ38号P.476参照
[7] 別冊判例タイムズ38号P.478,479参照